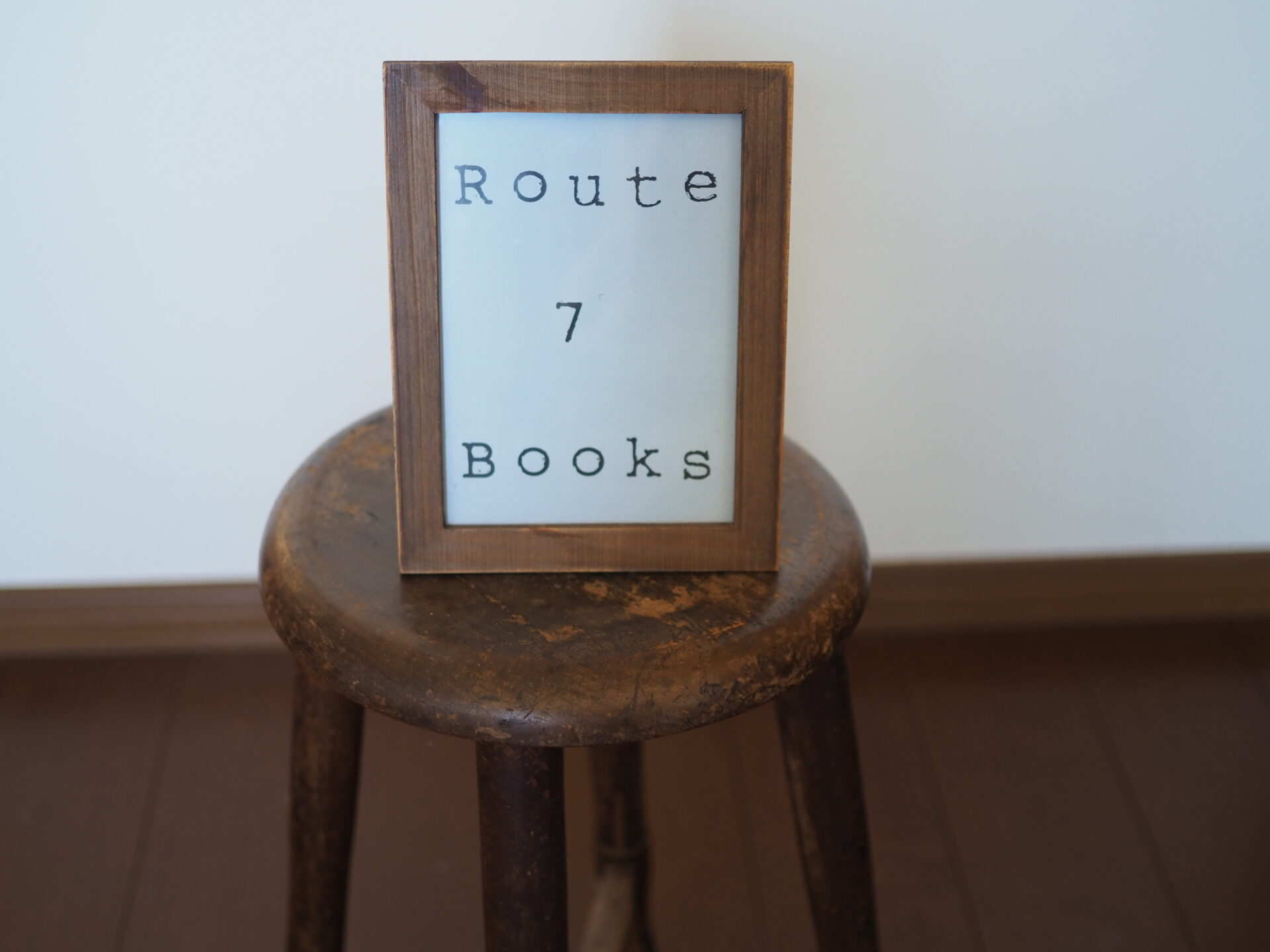作品の概要/あらすじ
- 同作品はイタリアの作家チェーザレ・パヴェーゼ(Cesare Pavese, 1908年9月9日 – 1950年8月27日)により1950年に発表された長編小説。同年に作家が自殺し同作品が最後の長編小説となった。
- パヴェーゼの故郷でもあるイタリア北部のトリノ近郊の寒村が舞台
- この小説は、イタリアの貧しい村に孤児として育ち、極貧の生活から抜け出し財を成して数十年ぶりに故郷に帰ってきた「ぼく」が物語る話。
- 『「ぼく」が村に滞在する間に起こったこと、かつての自分のような男児と知り合い、その男児にもある事件が起きる』『「ぼく」の過去の話、孤児として生まれ、極貧の村に養子として迎えられる、また一家が立ち行かなくなったため、館に奉公する、世界への憧れ、手に入らないものへの焦燥や怒り、友人との青春とアメリカに渡った経験』『友人や村人から聞かされる男の不在中の戦争と死の話』などが入り混じる
- ぼくはみずからの半生の語り手でもあり、村での休養の間の村の傍観者でもあり、友人から戦争に関する話を聞かされる傍観者でもある。それらの時系列が重層的に折り重なるが、結局ぼくは「すべては季節はめぐり還る」という認識を強くする。
故郷へ帰り着いた男、故郷に残り続けた男
故郷の記憶/季節の匂い、収穫のとき
あのころのすばらしさは、すべてが季節どおりになされたことだった。そして季節は、 労働と収穫と、荒天と晴天とに応じて、それぞれの習慣と戯れとをもっていた。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
バールから出たとき、 汽車に乗りかけたとき、あるいは夕がた帰ってきたとき、ふと、空にぼくは季節の匂い せんてい を嗅いでいた。剪定や、取り入れや、硫酸銅の撤布や、桶を洗ったり葦を刈り取るのは いまだ、とぼくは思い出していた。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
この暑さが、ぼくは好きだ。それはひとつの匂いを持ってい る。この匂いのなかにぼくも存在している。このなかに、たくさんの収穫と乾し草と夢 窓とが、もはや自分の体内にあるかどうかもわからぬ、たくさんの味と願いとが、存在ている。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
そしてぼくは、まるで生まれ変わったかのようにこの村に帰ってきた、貧困の幼少時代に会いに
故郷の生活/農村の営み
ヌー トは、決してここを離れようとしなかったのだが、それでも世界を知りたい、事態を変 えたい、季節の鎖を断ちたい、と願っていた。いや、そうではなくて、たぶん彼はつね 月を信じていたのだろう。けれどもぼくは、月を信じていなかったから、要するに季 節だけが大切であり、おまえの骨をこしらえたものは、子供のときにおまえが食べたも のは季節だ、ということしか知らなかった。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
過ぎていった青春/手に入らなかった憧れ
汽車に乗ればどこへでも行ける し、鉄道が終われば港が始まり、船は定刻どおりに出航して、世界じゅうの道と港は交 差し、時刻表に則って人びとは旅をし、物事を作ったり壊したりしている、 そしてどこ にでも有能な人間と無能な人間とがいるのだ、と言ったのは、やはりヌートだった。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
黒ぐろと丘を照らし出した月夜の晩に、ヌートが尋ねた。 アメリカへ行くとき、どう やって船に乗ったのか。もしも二十歳に返って、同じ機会に恵まれても、やはりそうす るか。ぼくは彼に言った、アメリカに行きたいからというよりは、自分が何者でもない ことに対する怒りから、そうしたのだ。立ち去りたいというよりは、いつかみながぼく を飢え死にしたと決めこんだ日に、帰ってきたかったからだ。 村にいれば、ぼくはひと りの下男になるしかなかったろう
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
「月と篝火」とともにある農村/祭りと貧困と戦争
そ して刈株のなかの篝火の話を、ぼくがしたときにだけ、顔をあげた。「たしかに良いこ とだ」 いきなり彼は立ちあがった。「大地を目覚めさせるのは」
「でも、ヌート」 ぼくは言った、「チントでさえそれを信じないのだ」 やはり、と彼は言った、あの子も知らないのだ、熱のせいか炎のせいか、何が水気を 呼び覚ますのかともあれ、畑の端で火を焚いたときには、必ずはるかに水気の多い、はるかに質の良い、収穫がえられる。
「それは初めて聞いた」と、ぼくは言った。「それならば、きみも月を信じるのか い?」
「月は」とヌートが言った、「嫌でも信じなければならない。満月の夜に松の木を伐っ てみろ、蛆虫に食い殺されるから。 葡萄の桶は、月が若いうちに、洗わなければいけな い。 葡萄の挿し木だって、新月のうちにしなければ、根はつかない」
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
形を変えて現れる「月と篝火」のイメージ
月と篝火の話も知ってはいた。ただ、ぼくは気づいていた、もはやそれを知っているとは言えないことに。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
祭りの祝祭性、儀式をはらむもの、農村生活の一環としての祭り
農村の秘密/繰り返される性と暴力
貧困の果て/こうであったかもしれない人生
ベルボの谷間から彼は一歩も出なかった。いつのまにかぼくはあの小径に立ち止まって考えていた、もしも二〇年前に逃げ出さなかったら、それはぼくの運命でもあったのだ。けれどもぼくのほうは世界じゅうを、彼のほうはこのあたりの丘の世界をさまよいつづけた。そしてさまよいつづけながら、ついにふたりとも口に出して言うことはな かった、《これがぼくの持物だ。この横木の上で自分は年をとるだろう。 この部屋のなかで死ぬだろう』とは。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
娘たちの最期/篝火
葡萄畑からたくさんの枝を伐ってこさせ、見えなくなるまで彼女を覆った。そしてガソリンをかけ、火をつけ た昼にはすっかり灰になっていた。去年までは、まだそこに残っていた、篝火を焚いたような跡が
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
死んでいくもの/残り続けるもの
奇妙なことに、すべてが変わってしまったようでありながら、やはり同じだった。昔 の葡萄の樹は一株も残っていなかったし、家畜もそうだった。いまでは牧草地は麦畑に なり、麦畑は葡萄畑になり、人びとは移ろい、成長し、死んでいった。 木の根は崩れて、 ベルボ川へ落ちこんでいたにもかかわらず、あたりを見まわせば、ガミネッラの大 きな山肌が、遠くサルトの丘から丘をめぐる小径が、麦打ち場が、井戸、人声、そして きらめく鍬が、すべてが少しも変わらずに、すべてがあの匂いを、あの気配を、昔のあ の色あいをとどめていた。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
ぼくは思った、何もかも同じなのだ、同じ姿ですべてが立ち返ってくる かつてふたりの姉をぼくが連れていったように、二輪馬車に乗せて、あの丘から丘 を、サンタを連れて祭にゆくヌートの姿がぼくには見えた。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
故郷の意味/まためぐり帰るために
故郷は要るのだ、たとえ立ち去る喜びのためだけにせよ。 故郷は人が孤独でないことを告げる。 村人たちのなかに、植物のなかに、大地のなかに、おまえの何かが存在しおまえがいないときにもそれが待ちつづけていることを知らせる。
ーパヴェーゼ『月と篝火』河島英昭訳 岩波文庫
「月と篝火」に基づいた農民的な世界と通底する戦争と暴力、貧困と性によって血が流されるということ
それらを越えて季節は巡り、同じことが脈々と繰り返されること
それらの暴力と血の匂いが傍観者であるぼくを引き寄せる、まるで「故郷」のモチーフのように、故郷はそこに住む人間の暗部を隠しながら、それでも季節はめぐり、同じことは繰り返される。そしてその一方で、季節は巡りながらも流浪するぼくに残り、孤独ではないようにする