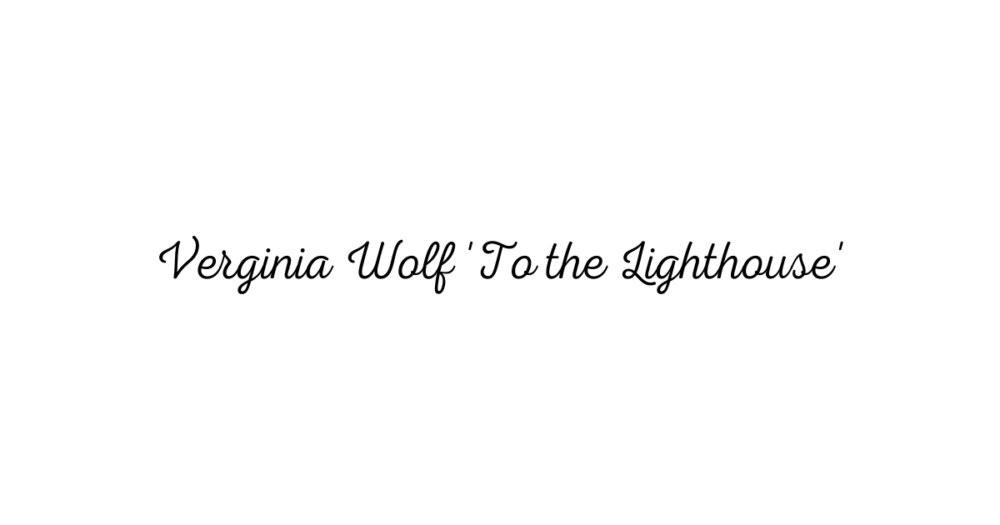「調和」と言われると、何を思い浮かべますか。私は教室の黒板のうえに掲げられたいかめしいスローガンを思いだします。例えばこんな学校を思い浮かべてください。
休み時間を思い浮かべてください。子どもたちは教室内で無秩序にばらばらに遊び、ある子は泣かされて、ある子は怒っている。
けれどもひとたびチャイムが鳴り、あの先生が入ってくる。もしその先生が少し世話焼きで昔なところがあっても、子どもたちを結び付ける、「調和」というものを生み出すことができる先生であれば、子どもにぎくしゃくしていた場が和んで、一体感が生じ、さっきまで仲が悪かった子とも、結びつくことができる。自分とはまったく性格の異なる子ともうまくいく。クラスがひとつの生き物のように感じられ、隣の子が何を考えているのかわかるようになり、ひとつになる。この一体感の中、この瞬間を忘れたくない、ずっと続けばいいのに…と思うかもしれない。
一方、子どもたちを指揮することができない先生を思い浮かべてみましょう。学級が崩壊し、ばらばらの状態。そして、泣かされた子は泣いたまま、怒った子は怒ったまま、それぞれ孤独のままに時が過ぎ、やがて学期が終わり、子どもたちは別々のところへ去っていく。わずか一時、気の合うもの同士結びついても、すぐに切り離され、ばらばらになる、高揚した一体感はない
ひととひとを結び付ける見えない能力のある人、いませんか。あるいは教師ではなく、職場の上司や、兄弟のいる方にとっては親、友人でも同じことかもしれない。こうして、異なる存在同士が結びついたりまた離れたりするのはとても不思議なこと。
この小説は、登場人物たちがどんなストーリーをつむぎ出すのか、というよりは、「異なる存在が結びつけられ、調和が生まれることの不思議さ」といった、抽象的なテーマにより描かれているため難解。そもそもストーリー自体に動きはない。しかし、この挑戦だからこそ、きわめて切迫した、切実な疑問に正面から答えたのがこの小説
失われた調和をいかに取り戻すか、それこそがこの作品のテーマではないでしょうか。
作品の概要/あらすじ
- ヴァージニア・ウルフが1927年に出版した5作目の長編小説。
- ストーリーよりも登場人物の思考や考察が多くを占めており、プルーストやジョイスの作品と並び、しばしば現代小説の代表作のひとつとして挙げられる。
- ウルフ自身は「私が書いた本の中で迷わず一番といえる一冊」と語っている。
- スコットランドのスカイ島を舞台に、ラムジー一家とその別荘に夏の間滞在した客の様子が描かれる。
- 3部構成となっており、第1部で一家と客たちの人間模様が描かれ、第3部ではその10年度の姿が描かれる。さらに、第2部ではその10年間の時の流れが描かれる。この第1部から第3部までの10年間で、一家には決定的な変化が起こる。この物語は、その決定的な変化からもう一度再生する一家の物語。
- 特に物語の中心的な役割を果たすのが第1部ではラムジー夫人と第3部では画家のリリー・ブロスコウ。ラムジー夫人はヴァージニア・ウルフの実母、リリーはウルフ自身が反映されていると言われる。
※ネタバレあります!※
海沿いで過ごしたとある一日/移り変わるそれぞれの思い
こうしてラムジー氏がテラスを住 き来し、 夫人が窓辺でジェイムズとくつろぎ、空には雲が流れ、風を受けた木がしなる ところを見ていると、いかに人生というものが、もとはバラバラな体験の連続であって も、やがて渦を巻くようにまとまって一つの大きな波となり、いわば人はその波ととも に高く盛り上がっては、勢いよく岸辺に自らを打ちつけるに至るものかが、いやでも 生々しく感じ取れるのだった。ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
この小説は、登場人物の目に見えない関係の網の目と力関係、それらが瞬間ごとに移り変わるさまを描く
ウルフの小説内では、移り変わらないものがない、「あのひとは耐えがたいほどに憂鬱な気性だ」と評していたと思えば、そのすぐあとに、ふとしたきっかけで、「でも場の空気を和ます独特のユーモアを持っている」など、ころころと移り変わる
また、しばしば同じものに相反する気持ちを抱える
それぞれの登場人物が相反したり移り変わったりするので、小説自体も、てんでばらばらになりそうになりながら、ウルフの筆によりまた結びつき、瓦解しない
この小説の魅力はストーリーのおもしろさではなく、むしろそれぞれの登場人物の意識が波のように寄せては返しながら、晩餐会をクライマックスに「調和」が描かれる、すべての関係は移り変わるが、第1部においては晩餐会を目指して「渦を巻くようにまとまり大きな波となる」
そしてその絶え間ない運動の中心にラムジー夫人がいる。
冒頭で一家が灯台に向かう予定を立てている場面で始まるが、暗雲が立ち込めている。
惜しみなく与えるもの/奪い取るもの
しかしこうして夫を包み込み守る力を誇っているうちに、 夫人自身のものと呼べるものは、ほとんど何も手許に残らなくなった。すべては惜しみ なく与えられ、使い果たされてしまったのだ。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
特に目を引くのが、ラムジー夫人とラムジー氏の夫婦関係、ギバー(Giver)とテイカー(Taker)という言葉があるが、夫がいわゆる「テイカー」として描かれる、惜しみなく与えるものと奪い取るもの、
ただし、具体的な夫婦ではなく、また男性と女性を固定的にとらえているのではなく、むしろ「いわゆる男性性というもの」と「いわゆる女性性というもの」というように象徴的に描かれる印象、しかし、具体的な描写は損なわれず、本当に身の回りにいそうだ
夫人は身を捧げて調和をもたらし、その一方で夫はどこか子どもじみたように、かんしゃくを起こしたり露骨に不機嫌になって見せたりする
家庭に捧げられる人生/芸術に捧げられる人生
これだけは議論の余地がないわ、結婚しないということは(夫人は少しだけリリーの手を握っ た)、結婚しない女性は、人生最良のものを取り逃がしているのよ。確かにこの家全体 が、静かに眠る子どもたちとそれを優しく見守るラムジー夫人の気配にあふれ、シェードで和らげられた灯りや安らかな寝息に満たされているように思われた。でも、とリリーは言おうとする、わたしには世話をすべき父がいますし家もあります。 そしてあえて言うなら、絵だってあるんです。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
ラムジー夫人の調和は前時代的
少なくとも、と彼女はテーブルクロスの上の塩入れに目をとめつつ自分に言 い聞かせた、ありがたいことにわたしは結婚なんかしなくていい。あんな堕落をこうむ る必要もないし、自分を薄めてしまうこともない。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
リリーの葛藤、相反する感情、芸術(ヴィジョン)についてと結婚について、そしてラムジー夫人への愛情と結婚への憎しみについて
前時代の結婚を前提とした人生を送るラムジー夫人に対して、女性の多様な生き方を模索するリリー、それはただ年上の世代から説教されているだけではなく、結婚というものが人生における調和をもたらすものだと信じているから
けれどもリリーは芸術と共にそこに至りつこうとするのです
ひとつに溶け合う瞬間/人生の核心としての晩餐
何ひとつ溶け合うことなく、皆ばらばらにすわっている。そして溶け込ませ、 流れを生み、何かを創り出す努力はすべて彼女の肩にかかっていたのだ。反感をもつと いうよりただの事実として、夫人はあらためて男たちの不毛さを感じた。だってわたし がしなければ、誰もわざわざそんな役を引き受けようとはしないのだから。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
ウルフにおけるパーティの重要性、ばらばらのひとたちをひとつにまとめるということ、「調和・ハーモニー」の象徴
けれどもラムジー夫人の身を削るような不断の努力により成し遂げられるということ
そもそもこのパーティは何のためにあるのか?
きっと皆は、とまた歩きだ しながら夫人は思った、どんなに長生きしようと今晩のことは忘れないだろう。この月、この風、この家を思い出し、わたしの思い出を蘇えらせることだろう。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
具体的な描写と観念的な思考が両立する、目まぐるしく変わる、混ざり合うなかで、パーティが頂点をむかえる。パーティの後の満ち足りた空気の中で、ラムジー夫人はひとり考える。自分が身を挺して調和をもたらした今晩のパーティも、まったく虚しいものではないか?時が流れれば、それぞれがばらばらに生きることになるのではないか?さらに言えば、自分もむなしい存在ではないか。けれども、子どもたちに残るということ、受け継がれるだろうこと。
結局、灯台行きは悪天候により中止となり、歳月が流れ始める。
はるかな時の流れと残された別荘/ふたつの危機
灯台へ出かけること。でも何を持っていけばいいのか? 滅びゆく、一人にて。向かい の壁の灰緑色の光、誰もすわっていない椅子の列 それらはいずれも非現実感の紛れ もない一部分なのだが、それをどうやって結び合わせればいいのか?
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
10年の歳月は一家に戦争と病と、関係の変化をもたらす。10年後、一家は再び別荘に集うが、戦争をはさみ重大な変化が家族に起きており危機が訪れている。
ここで、本来であれば激動の第二部が簡潔にしか記されていない点に注目したい。本書を手に取ったことがある人であれば、第2部の薄さに驚いたはず、異質な構成。おそらく一般的な構成によりつくられた大河ドラマ的な小説感だと、この10年間は多くのページを割いて描かれ方をすべき。しかしウルフはあえてアンチドラマ、それはこの小説が、「人生はささやかな日常のうえにこそ立ち止まるものだ」と強烈に主張しているためではないか。
「一人にて」と彼がつぶやくのが聞こえた、「滅びぬ」と
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
ラムジー氏が繰り返すこのフレーズが響く中、第3部が不穏な空気に包まれて始まる。この小説の後半はこの問題提起にどう回答するかが描かれる
「滅びゆく、おのおの」とはどういうことか
- 家族の関係ががばらばらになること
- それぞれ孤独に死んでいくということ
ばらばらになった家族の不調和
ところがキャムの用意がまだできず、ジェイムズもぐずぐずし続け、ナンシ はお昼のサンドイッチを頼んでおくのを忘れる始末で、ラムジー氏はひどく腹をたて、 ドアをバタンと閉めて出て行ってしまった。「今から出かけて何になるんだ?」という怒鳴り声が響いた。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
一家をつなぎとめていた人物の死によって心が結び合わずばらばらになる、「不調和」
ひとりぼっちで滅んでいく孤独
まるで物事をつなぎとめていた絆が 切れ果てて、いろいろな物が、わけもなくあちらへこちらへと漂っているかのようだ。何の目的もなく、混沌としていて、まったく現実感がない、と空っぽのコーヒーカップ を見つめながら彼女は考えた。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
また、戦争は人間の脆さを描く、そんなばらばらの存在のまま孤独に死んでいく、特にことばは残酷にたった数行でその死を描く、
あるものは若くして、あるものは惜しまれて
断片的で細切れの言葉など、何の役にも立ちはしない。 「人生について、死について、 ラムジー夫人について」 いやだめだ、言葉で思いを伝えることはできない。その時 の思いにせきたてられて、いつも狙った的をはずしてしまうから。 言葉という矢は、ふ らふらと横にそれて、標的の数インチ下に中たるのが関の山なのだ。それで話すことな どあきらめてしまい、思いは胸の奥にしまいこまれることになる。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
それぞれの新しいつながり
「滅びる、おのおのひとりで」第3部はラムジー氏が何度も唱える不吉なリフレインと、そのことばが現実となっている場面から始まります。それぞれが滅びるということからいかに回復するか
新しく変わってゆけることへの祝福
やがて氏は、勝ち誇ったように叫んだ。
「よくやったぞ!」 ジェイムズの舵取りは、生まれながらの船乗りのように見事だっ たのだ。
ほらね、とキャムは心の中でジェイムズに話しかけた、ちゃんとほめられたでしょ。 これがジェイムズの求めていたものであることを、彼女は知っていた。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
「ひとりぼっち」という問題
残された家族は、ばらばらのまま、亡くした者の意志に突き動かされるかのように灯台を目指す。だれも望まないのに、なぜ灯台に向かうのか?作中では明確に語られていない。それは10年前に実現されなかった子どもたちの願望でもあるのかもしれないが、家族はみな明確に自覚もしていなければ導く人もいない、目的のない船出、失敗が目に見えている。
特に夫人の感受性を受け継いだかのような男の子は父親と葛藤している、父親の専制的な態度に抵抗
最悪の船出で出発したが、灯台に到着する寸前に、ふとした父親の一言で、関係が一気に変わる一言がある。
頑なに拒んできた関係が、一言でふと和んだり、まったく別のものになるということは日常的にある。これがウルフらしい。ただし、調和も不和も一瞬で、だからこそ読者は「あれ?」と混乱の中に落とされる。まるで、それは、良いことが永遠に続かないことを意味するが、同時に悪いことも続かないというように。
親父は専制的で押しつけがましくて四六時中人生に愚痴を言い続けている」と思ったが、最後のシーンで軽やかささえ感じさせる。
ウルフは小説家としてそれこそが人間の不思議さであり面白さと思ったのだ、むしろそれが人間の軽薄さや浅はかさと結びつくと思ったら、ウルフの小説はもっと悲観的
親子の関係性も同じ、「ほら、うまくいったでしょ」
まったく「神などいるものか」と言わんばかりだな、とジェイムズは思い、まるで何もない宙空に飛び立ってい くようだわ、とキャムは思った。そして父が包みをかかえて、若者のように軽やかに岩 に跳び移ると、二人も立ち上がって後に続いた。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
すべてのものは移り行くし、あまりに儚いように消え去っていくけれども、それは悲しいだけではなくて、新しいように変わっていけるよ、というメッセージのように読める
それは、変わっていけるということ自体が人生の祝福、救いなのだというようにも読める
ここにいないからこそ、不在だからこそラムジー夫人の存在が、すべてを調和させようとする意志が浮かび上がる
滅びゆくものたちの祈り/残り続ける意志
また、リリーにも夫人が残した意志による啓示と救済が訪れる
「ひとりぼっちで滅びる」
愛しいひとを失ったひとりぼっちのリリーの葛藤、リリーが追い求めるラムジー夫人はどこにいるのか?からっぽの踏み台、思い出の場所は不在を掻き立てる、それはもはや「言葉が役に立たない」、小説家であるウルフが言葉が役に立たないということのすさまじさ、ことばの限界、では言葉は何も役に立たず、不在は不在のまま、からっぽなのか?
夫人は何でもない瞬間から、いつまでも心に残るものを作り 上げた(絵画という別の領域でリリーがやろうとしていたように)これはやはり一つ ただなか の啓示なのだと思う。 混沌の只中に確かな形が生み出され、絶え間なく過ぎゆき流れゆ くものさえ(彼女は雲が流れ、木の葉が震えるのを見ていた)、しっかりとした動かぬものに変わる。 人生がここに立ち止まりますようにそう夫人は念じたのだ。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
「人生がここに立ち止まりますように」そんな啓示が訪れる
「滅びゆく儚く混沌とした存在の中で、パーティや絵画の形で「調和」を与え凝固させること」が夫人の役割だったし、また、リリーにとっての芸術の役割、すべてが虚無の中に流れていかないように、残るべきものがここに残るように
「人生はすべて流れ去り、何にも残らない無」ではなく、「人生がここに立ち止まりますように」、ラムジー夫人の祈りをリリーが見出す、日常の中の何でもないものから、人生が立ち止まるものを生み出すということ、例えば、そのためのパーティ
だから、人生は何も残らない無なんかじゃない、人生はそこかしこに残る、祈りや意志として、ひと時の調和により
「あなたがいない」ということを越えるために、役に立たないことばを越えて、その目に見えない残されたものたちと「つながっている」ということを感じること
結婚を含め安易な「調和」から距離を取っていたリリーに調和が訪れる
「つながっていることがわかり、孤独ではなく、満ち足りてある」ということ、日常の雑多なすべてのものや、この場所やこの家、なにか大きなものと繋がって、「在る」ということを感じられるということ
そのために芸術があるということ
ただ隣り合っているだけで、心がバラバラでは意味がない、もうそばにいなくても、そのひとの意志が感じられることが繋がりと言えることもある
そしてリリーもまた、ラムジー夫人の願いが成就するのを見届ける
去っていった人の意志は残り、遺された人たちは新しい関係でつながれ、ひとりぼっちじゃないと感じられる
その背後には、やはりラムジー夫人の調和がもたらされるべきという大きな意志が感じられる、「ほらね、大丈夫」と
人生が立ち止まるところ/残されたもの・家・場所
そもそも何かを話す必要などまっ たくないのだ。ただ広げた帆をゆったりとはためかせながら(入江では多くの小舟が動 き始めていた)、さまざまな事物の間を、事物を越えてすべるように進んでゆけばよい。 それは空しさとはほど遠い体験で、むしろ身体じゅうが満たされている感じだ。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
「ひとりでもさみしくないように」
若干抽象的な議論に傾きすぎているようですが、例えば素朴に、いまいないひと、離れているひとのことを考えると、そこまで実感のない場面ではないと思う。
ここにもういないあなたが私とつながっていると感じられること、そのためにはなにが必要なのか?肉体があって触れられるということだけではない。例えばもう二度と会えなくても、そこにそのひとの意志を感じられるようなとき。
けれどもそんな気配のような、あるいは一時の気分や妄想のような心境は、言葉になり得るのか?気のせいだと言われればそれきりかもしれないこの小説も、常にその危険をはらんでいる、それはリリーの一時的な気持ちの変化ではないのか?またすぐに孤独に落ちるのではないか?そもそも小説内で早々と「言葉の役に立たなさ」が繰り返される異常事態の中で、それでも小説家が描きたかったのは、「孤独の淵に落とされていたひとりの芸術家が、人生は虚無ではなく、なにものかが形となり残るという啓示を得て、つながりを再確認し、満ち足りる」ということ
それをストーリーに頼らず、物語の起伏に頼らず描くことは本当に冒険、ただし私は成功していると思う
人間たちが脱ぎ捨て、置いていったもの靴が一足に鳥打帽、洋服箪 筒の中の色あせたスカートやコートなど それらはかろうじて人間の形をとどめてい て、そのうつろさがかつて身につけられていた頃の生き生きとした動きを偲ばせ、ホッ クやボタンを留めようと、いくつもの手がいかに忙しく動いていたかを思い出させた。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
なぜなら、この小説は抽象的な観念の話ではなく、具体的な「残されたもの」、「場所」、「家」があって、だからこそこの小説ではものが別荘のものが詳細に残され、場所が描かれ、そして家の管理や様子が第2部を中心に細密に描かれる
個の肉体としての個人は儚くとも、ものや家や場所に残り、また残されたものを突き動かす意思として残り続ける、そしてその意志が成就した時に、ばらばらだった残されたものの心にも新たな関係が訪れている
この作品は、ことばの限界に迫りながら、救済と再生の物語
不在であるはずなのに、逆にラムジー夫人が、その意志が「在る」と「感じられる」のがこの小説のすごさ
ウルフの小説家としての挑戦、冒険のすさまじさ、ことばの限界を知りながらそこに挑んでいくこと
海のそばの別荘/スカイ島の美しい風景と自然
が、ここで町の家並みが途絶え、波止場が見えてきたと思うと、突 然目の前に湾全体が大きく広がり、思わず夫人は「まあ、なんてきれいな!」と声をあ げた。巨大な水盤を満たしたような一面の青い海が眼前に横たわり、その中央に灰白色 の灯台が遠く、厳かにそびえ立っていた。右手の方には、風になびく野草の生えた緑 色を帯びた砂丘が、霞んだりくぼんだりしながら、なだらかな襞を描きつつ果てしなく 続いていて、見るたびにいつも、人の住まわぬ月の世界に通じる道を偲ばせるのだった。
ーヴァージニア・ウルフ『灯台へ』御輿哲也訳 岩波文庫
筆者の雑感ですが、スカイ島の自然にも啓示を呼ぶような力がある
ロンドンの街中の揺れ動く気分ではなく、荒涼とした自然の中で「満ち足りて、在る」ことの啓示を受ける
ストーリーテリングという大々的な手段ではなく、むしろ日常を取り上げ、そのなかにこそ救済や再生が含まれているとするウルフの文学にふさわしい場所に思える