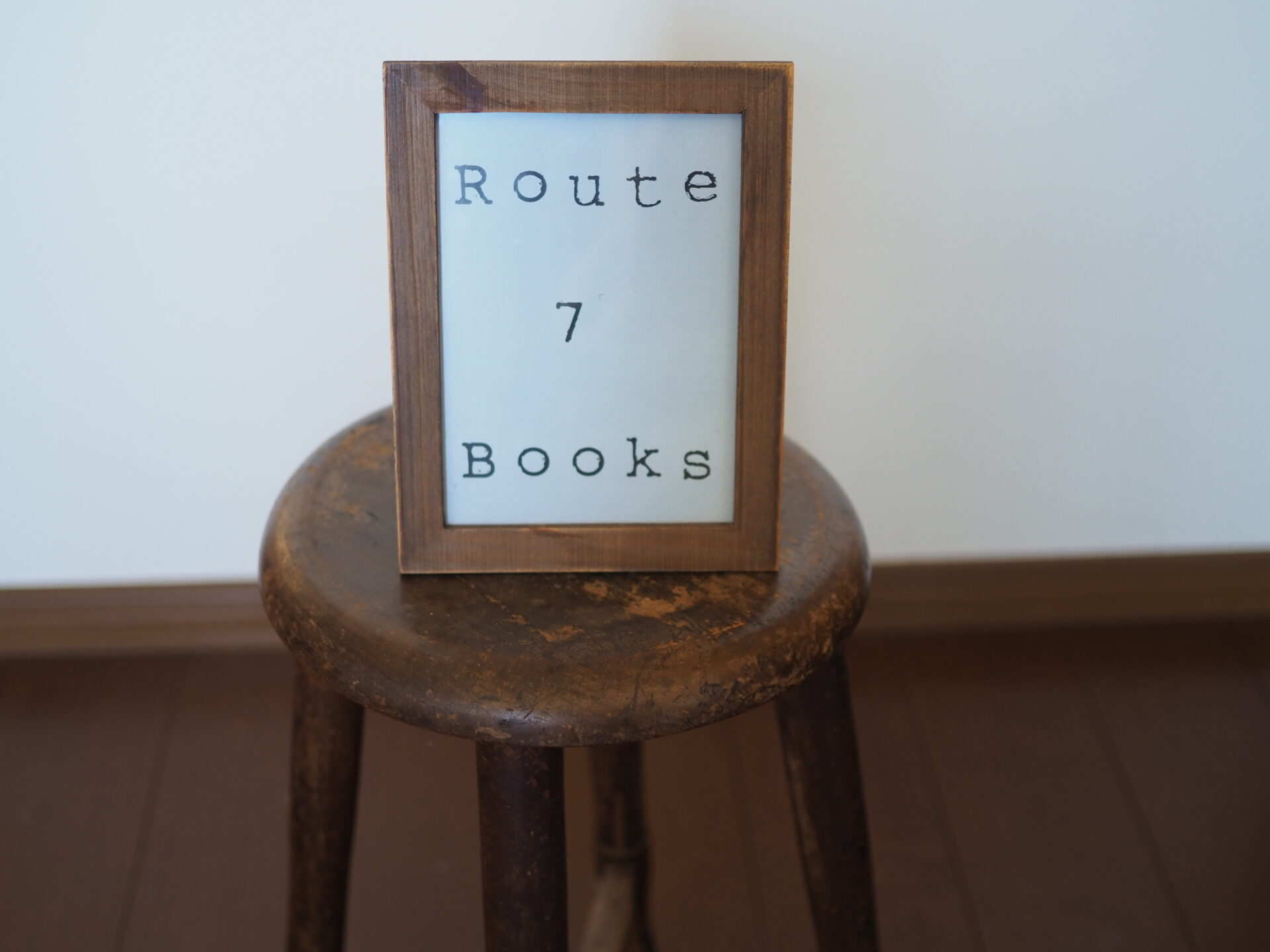「あなたは誰ですか。」と聞かれてすぐに答えられるひとは少ない。答えられるのだとすれば、よほどひとつの物事に人生を賭けているひとなのかもしれない。私とは誰なのか、年齢や職業、社会的地位や生まれ育った場所、配偶者の有無や収入状況など、客観的な事実を挙げるほどに、私というものは逆にわからなくなっていく。だからこそ自分探しということばが生まれるのだろう。
むしろ、「私」というものは、「私のように感じられるもの」の寄せ集め、つまり「私のように感じられるもの」の集合体ではないか。「私」というものがあるわけではなくて、その時その時で変わっていく「私に近しいと思われるもの」の寄せ集め・つぎはぎが「私」を形作っているように見えるというだけで。さらに言えば、「私のように感じられるもの」の寄せ集めは、つまり「私でないと感じられるもの」を通して見えてくるとも言える。
例えば、辞書に乗っている言葉を片っ端から私のような言葉と私ではない言葉と、関係のない言葉に分けたら、そこに私のようなものが浮かび上がるかもしれない。
例えば、メジャーとマイナーの無数のコードをつなぎ合わせて、ある進行を生み出す場合、その響きの中に私のようなものが聞き取れるかもしれない。
例えば、色のグラデーションのなかからいくつかの色を選んで白紙を塗り上げた場合、その色合いの中に私のようなものが感じられるかもしれない。
どれだけ自分を創造しようとしたり、創作しようとしたりしても、結局、私というのはどこか奥底にある固有の実態ではなくて、うつろな空洞、ただの寄せ集めであると思う。そして私と他人の間には曖昧な境界があるだけ。
そんな「私」が脅かされるときが、必ず誰にでも訪れる。それは「私」を形成しなければならない思春期のとき。そして、その後、私が揺らぐような激変があるとき。ひとが「私」を再び形作ることを余儀なくされるとき、それは極めて個人的なこととなるから、ひっそりと行われるはず。しかし、もしそのドキュメントが残されていれば、そしてそれが、ジョン・レノンのものであるとすれば。
楽曲の概要
- 1970年に「プラスティック・オノ・バンド/Plastic Ono Band」名義で発表されたソロ・アルバム「ジョンの魂/John Lennon/Plastic Ono Band」のクライマックスを飾る楽曲。
- ビートルズの活動と並行して1968年から前衛的なソロ活動を開始していたジョンだったが、1970年4月のビートルズの解散直後から、幼少期の記憶にまで遡って、すべてを吐き出すという精神療法「原初療法(Primal Therapy)」を受けており、同楽曲にはその影響が如実に表れている。
- 「ジョンの魂/John Lennon/Plastic Ono Band」全体がジョンのありのままの苦悩や葛藤を表現したシンプルかつ悲痛な内容であり、それに呼応するかのようにアレンジも最低限のバンド・サウンドのみで構成されている。
わたしを越えたものの不在
God is a concept by which we measure our pain
-John Lennon “God”
この楽曲は、「God」を定義する一文から始まります。難解であり、かつ多様に解釈できる一節です。少なくとも、ここでは「God」について定義づけを行っていること、そして、その定義によれば、「God」はある概念であり、苦痛を図るための手段でしかないということ。さらに言えば、例えば私たちの世界そのものを形成する根本にあるような、私たちを超えた存在ではないし、また、私たちのうえになにか世界像があるのではないということ。
つまり、少なくとも私たちを超えた存在として捉えられていないということ。逆に言えば、私達を超える存在がないということを言っている。
否定の果てに見出されたなにか
I don’t believe in Beatles
-John Lennon “God”
固有名詞を並べて、否定していきます。宗教や主義主張、個人名が名を連ね、この楽曲中最もインパクトがある個所です。そして、これらはここに並べられた物事を否定・攻撃することが趣旨ではなく、「私」から、これまで「私」に絡みついて、「私」を縛って制限していた物事すべてを切り離すことが趣旨であるように思います。
「私」が「私のように感じられるもの」のあいまいな集合体である以上、時に「私のように感じられるもの」があまりにまとわりつき、私が肥大化し、私がわからなくなるということが起きる。だからこそ、私という集合体にいつの間にかこびりついてしまったものをひとつひとつ引きはがし、限界までそぎ落とすことで、見失った「私」をもう一度見つけ出そうという営みなのです。まるで、私から一切の肉をはぎとり、一度骨だけにするかのような。
しかしながら、先の節で単なる観念と定義された「God」を含め、ここで挙げられた観念は、当時のジョンにとって、どんな世界にいて、どこから来てどこへ去っていき、なにが良くて何が悪いのか、これらを形作る基礎となるものたちであったはずです。ジョンは「私」を見出すことができるのか。
あいまいでからっぽのわたし/わたしがもう一度始まる場所
I just believe in me, Yoko and me, and that’s reality
-John Lennon “God”
私ははじめてこの一節を中学時代に聞いたときに、感動的である一方で、これまでの否定の力に比べてなんとうつろで頼りないのだろうと不思議な気持ちになったのを覚えています。そしてさらに、「ジョンの魂」というアルバム自体、この曲をクライマックスに(厳密にはもう1曲、「母の死」という最も個人的で、最も感動的な小品が収められていますが)投げ出されるように終わります。すべてを否定しつくした後に、「私だけを信じる」と言われても、その「私」とは、なにも入っていない空っぽの器のように感じられる。
けれども、まさにここでのジョンの「私」は空っぽの器なのではないでしょうか。だからこの歌は終わりの始まり、ここからジョン・レノンという私を、ジョンの魂というアルバムの各曲が再構成していく出発点にある歌なのです。まず、私がいまここにあるということ、ジャケットがすべてをあらわすように、そしてそこから、子供時代や大切な母からおいていかれたこと、そして失ったことを見つめ直していくこと。だからこそ、終わりにして新しく始まる場所。
すべてを否定しつくして、空っぽの私がもう一度「私」を再構成する始まりの地点。そう考えた場合、この個所の、寂しくもどこかすがすがしい響きが納得できるのではないか。
夢が崩れ去ったあとの孤独/空の青さ、木々のみどり
And so, dear friends
You’ll just have to carry on
The dream is over
-John Lennon “God”
この楽曲に関して、もうひとつ重要なことばが「夢」です。ここで語られる夢とは何なのか?それはつまり、ジョンが否定したそれぞれの概念。共同幻想という言葉がさらにわかりやすいのですが、夢がみんなの「私」に深く食い込んでいくほどに、それは信仰にも似た熱狂的な営みとなる。ここでいう夢=共同幻想とは、必ずしもビートルズという個別の出来事をさすばかりでなく、宗教、政治、または恋愛や友情、あらゆる人間関係のこと。そしてさらに事態を困難にしたのは、「夢織り人」としてまさにジョンはその核心にいて、旗を振っていた張本人なのです。
共同幻想という夢が終わって、曖昧な私達がバラバラになって、その挫折のあとに、ただ「曖昧なあなたと私」だけが残されて、そしてそれでも日常は続き、生活を続けなければならない。
ただあるということ、それはただ見上げれば空があるということ、すべての根幹にあるのはジャケットのように、ただあるということ、所有も観念もなくあるということ、曖昧でうつろで、その時々に移り変わっていく私を認めるということ
次作イマジンへ、イマジンの核心は、世界平和を新しい集団で夢見ることじゃなくて、観念や主義主張から離れ、ただ私達がいるということに注目すること、みんながその日暮らしで所有もなくなれば、その結果として平和になるかもね、ということだと思う。まさにその根幹にあるのは、強硬に私を主張し所有を認め自他を区別していく強固な「私」ではなく、曖昧な寄せ集めとしての「私」ではないでしょうか。私とあなたの境界線があいまいな、そんな場所で所有することもなくその日暮らしをする私たち、そんなある意味「空を眺めるような」生活の先に、いつの間にか平和が訪れているのかもしれません。